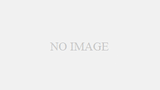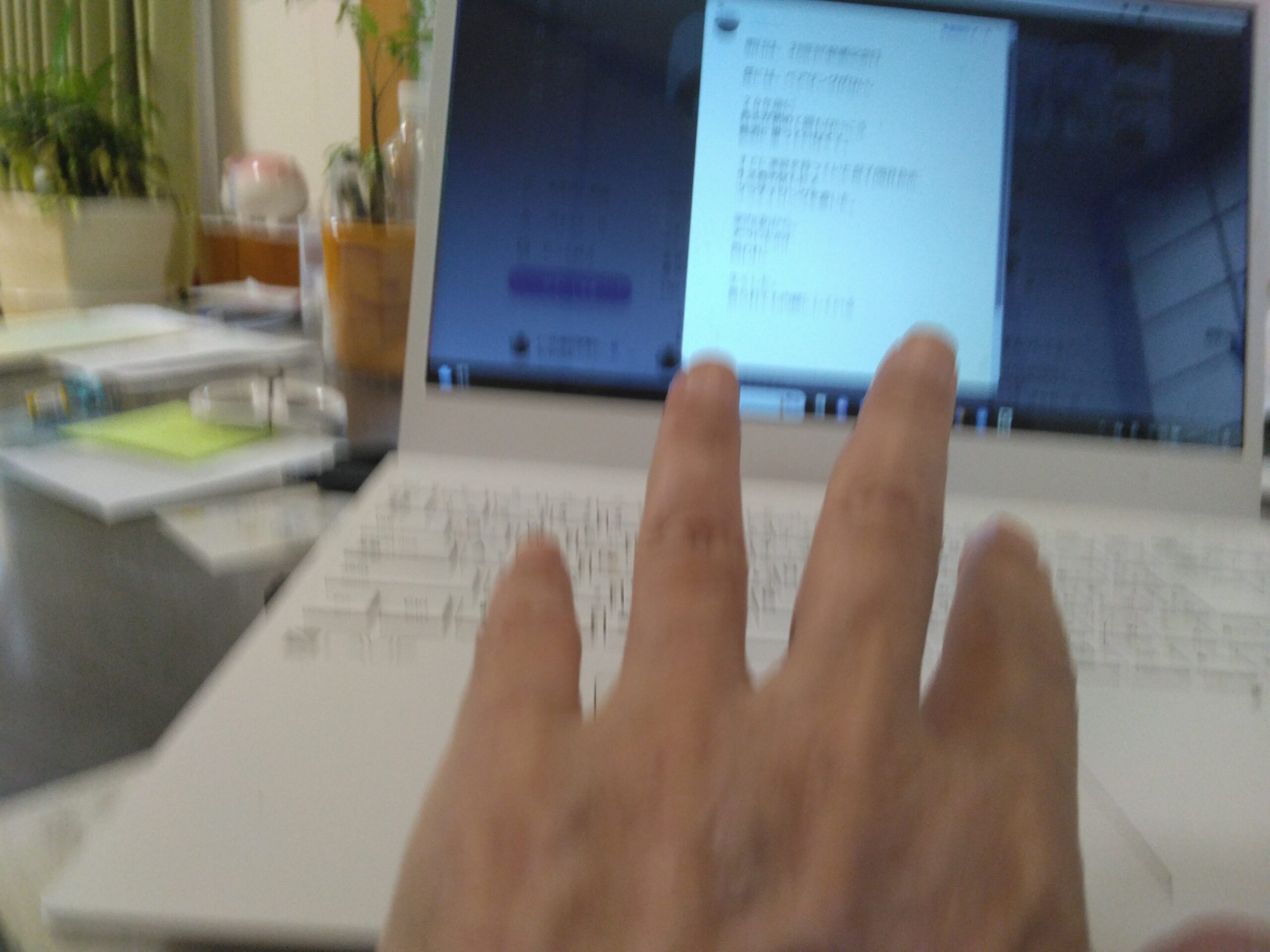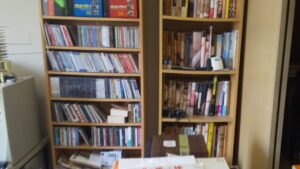賃貸物件の退去還去時、敷金の返還や原状回復費用に関するトラブルが発生しやすく、借主にとって負担になりますね。これらの問題をスムーズに解決するためには、事前の知識と第三者機関の活用が重要です。本記事では、退去時によくあるトラブルの具体例と、消費生活センターを活用した解決方法について解説します。
相談専門ページ
遺品整理 |生前整理 |空き家片付け |ゴミ屋敷片付け |家財整理
家財整理センターの案内
家財整理センターでは、遺品整理、生前整理、ゴミ部屋の清掃など多岐にわたるサービスを提供しています。専門のスタッフが、お客様の大切な思い出や空間を心を込めて整理・清掃いたします。ニーズに合わせた丁寧で迅速な対応を心がけています。コラムでは、整理整頓のコツやお役に立つ情報を定期的に配信し、安心してご利用いただけるよう努めております。
賃貸退去のトラブルの原因元である大家さん側と賃貸人双方から起きますのでこの両面から情報を収集しまとめました。消費生活センター(上部組織:国民生活センター)の寄せられたトラブル件数は、年々増加傾向にあるとのデータです。消費生活センターでは、消費者に”住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう“をキャッチコピーで啓蒙しています。
大家さんに起因する退去トラブル
賃貸退去に関するトラブルはさまざまな原因によって発生することがあります。以下に、消費生活センターに寄せられた大家さん側の原因によるトラブルの一部を挙げます。
敷金の不当な引き留め
大家さんが、適切な理由なく敷金を不当に引き留める場合があります。敷金は、退去後の清掃や修繕費用などに充てるためのものですが、契約違反や明らかな損壊がない場合には、適切な範囲内でしか引き留めることはできません。
具体事例を見てみる
ケース1:経年劣化による修繕費の請求
退去時、入居者が通常の使用範囲内で発生する壁紙の色あせや床の擦り傷に対して、大家さんが敷金を差し引いたケースがあります。この場合、契約書や国土交通省のガイドラインをもとに交渉し、不当な請求であることを説明する必要があります。
コメント:
経年劣化の負担は大家側にあると定められており、不当な請求には適切な手続きが可能です。写真や契約内容を提案し冷静に話すことが重要です。
ケース2:原状回復費用の過剰請求
入居者が退去後、全室の壁紙やフローリングの張り替え費用を敷金から差し引かれたケースです。 実際には一部の汚損のみが入居者の責任であり、全体的な改装費用を負担させるのはこの場合、具体的な損傷箇所を特定し、修理費の適正な範囲について検討が必要です。
コメント:
原状回復費用は入居者の不満部分に限られるべきであり、過剰請求には法的根拠を求めることが重要です。消費生活センターなどへの相談も有効です。
解約時の不当な手数料の控除
退去時に大家さんが解約手数料を請求する場合があります。しかし、契約書や借家契約法に明記されていない場合や法的な根拠がない場合には、手数料の請求は不当です。
具体事例を見てみる
ケース: 解約手数料として敷金から不当な差し引き
退去時、大家さんが「退去手数料」として敷金から数万円を差し引いたケースがあります。入居者が契約書を確認したところ、契約手数料に関する記載がなく、また退去時の契約解除に伴う費用をしかし、大家さんは「一般的な合意例」と主張して請求を続けました。
コメント:
解約手数料が契約書に信用がない場合、法の根拠がないため請求は不当とされます。このような場合、入居者は契約書をもとに主張し、不当放棄である旨をまた、「借地借家法」に基づき、賃貸契約において義務付けられていない費用を入居者に負担させることは有効とされる可能性が高いです。
消費生活センターや専門家に相談し、必要に応じて法的な手段で対処することをお勧めします。不明確な「慣例」に基づいた請求には注意が必要です。
契約内容の変更で敷金から控除
退去時に大家さんが一方的に契約内容を変更しようとする場合があります。たとえば、敷金の増額や退去日の変更などです。契約書に基づいての変更でなければ、大家さんの一方的な変更は無効となります。
具体事例を見てみる
ケース:ペットの飼育で特殊な清掃費も不要だったが請求された
入居途中でペット飼育が許可された際、「特別清掃費は不要とされます」と口頭で説明していましたが、退去時に大家さんから敷金の一部を特別清掃費として請求されました。費用内容に関するは契約書や合意書に記載がなく、居住者は「書面での根拠がない」として適当を申し立てました。
コメント:
特別費用の請求は、契約書や合意書に基づいていなければ法的な根拠がありません。 口頭説明だけ頼らず、必ず契約変更内容を記載した書面を確認し、保存しておくことが大切です。不当請求が発生した場合は、契約書や証拠を基に冷静に対応し、必要に応じて消費生活センターや専門家にご相談しましょう。
傷害賠償請求の過剰な請求
大家さんが、退去時に通常の使用による傷みや摩耗も含めて、過剰な傷害賠償請求を行う場合があります。賃貸住宅では、通常の使用による傷みは借主の責任ではなく、大家さんが負担すべきものです。
具体事例を見てみる
ケース1:壁紙の全面張り替え費用の請求
退去時、子どもが遊んで壁に小さな汚れをつけてしまったことを理由に、大家さんが部屋全体の壁紙を張り替える費用を敷金から譲ろうとしたケースです。が破損しており、全面張り替えは必要ない状況でしたが、大家さんは「統一感を尊重するため」として過剰な請求を行いました。
コメント:
損害賠償請求は実際に発生した損傷部分の修繕費用に限定されるべきです。 経年劣化や通常使用の範囲を超えた損害に対する修繕費のみが検討です。を依頼し、過剰請求にあたりを申し立てるべきです。
傷が付いた床全体の張り替え費用の請求
家具の移動中に床に小さな傷が付いてしまったため、大家さんが部屋全体のフローリングを張り替える費用を請求したケースです。 傷は1か所のみで部分補修が可能な状態でついでに、大家さんがさんは「見た目を整えるため」として高額な費用を求めました。
コメント:
損害賠償請求は、交換に対する適正な修繕損害費用に限定されるべきです。部分で補償可能な場合は、全体張り替えをする請求のは不当とされる可能性が高いです。契約書やガイドラインに沿って、適切な範囲で費用を主張しましょう。必要に応じて専門家に相談することも推奨です。
これらの問題は、契約書や借家契約法に基づいて対処されるべきです。もし大家さんとのトラブルが発生した場合は、消費生活センターや行政機関に相談することで、適切なアドバイスや解決策を得ることができます。また、法的な問題がある場合には、弁護士や法律専門家の助言を求めることも重要です。
入居者に起因する退去トラブル
賃貸の退去トラブルはさまざまな形で発生することがあります。以下にいくつかの事例を挙げます。
- 故意的な損害: 賃借人が退去する際に、意図的に物件を損傷する場合があります。例えば、壁や床に穴を開けたり、タバコの焦げ跡や染みを残したりすることがあります。これは保証金の返還を巡る問題となります。
- 清掃不備: 賃借人が退去する際に、清掃が不十分な状態で物件を返す場合があります。例えば、ゴミや埃が残っていたり、キッチンや浴室などが汚れている場合です。これにより、オーナーや管理会社が追加の清掃費用を請求する可能性があります。
- 家具や備品の不法持ち出し: 賃借人が退去する際に、家具や備品を不法に持ち出す場合があります。これは盗難行為となります。賃借人は、賃貸契約で定められた家具や備品を元の状態で返す責任を負っています。
- 定められた期間内の退去: 賃貸契約で定められた期間が終了する前に、賃借人が退去する場合があります。これは解約違約金の支払いや未払い家賃の問題を引き起こす可能性があります。
- 未払い家賃: 賃借人が退去する際に、未払いの家賃がある場合があります。これにより、オーナーや管理会社が未払いの家賃の回収を求めることになります。
これらは一般的な事例であり、賃貸の退去トラブルは個別の状況によってさまざまな形で発生する可能性があります。退去時の契約書や法的な規定に基づいて適切な対応を行うことが重要です。トラブルの解決には、賃借人とオーナーや管理会社の間での交渉や、必要に応じて法的手続きが行われることもあります。
国民生活センター賃貸住宅トラブルページより
国民生活センター 賃貸住宅の賃貸トラブル
- 賃貸アパートを退去後、原状回復費用の清算書が届いた。入居時から傷ついていた床等の原状回復も求められ納得いかない。
- 10年以上住んだ賃貸アパートを退去したらクロスの張替えなど高額な原状回復費を請求された。全額支払う必要があるのか。
- 6カ月居住した賃貸アパートを退去した。玄関の壁紙のわずかな傷で全面の張替え費用を請求され不満だ。
- 管理会社の了解を得て賃貸マンションの光回線工事をしたが、退去時に、工事は許可していないと言われ、原状回復費用を請求された。
- 賃貸マンションを退去したところ、高額なハウスクリーニング代を請求された。納得できない。
- ※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。
国民生活センターから消費者へのアドバイス
- 契約する前に、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
- 入居する時には、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。
- 入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
- 退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
- 納得できない場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談してください。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
国民生活センターの賃貸トラブル報告書より
敷金返還や修理代請求トラブルの無料相談先
入居者さんが退去のトラブルで相談したい場合は最寄りの消費生活センターのご利用がお勧めです。消費生活センターは、消費者トラブルの解決や消費者保護に関する相談に応じる行政機関です。相談は無料で受け付けており、専門の相談員が丁寧に対応してくれます。相談には、電話やメール、直接窓口での相談など、様々な方法があります。また、一部の消費生活センターではオンライン相談も受け付けている場合がありますので、自分に合った方法で相談することができます。こちらのコーナーで解説
賃貸契約において、敷金返還や原状回復に関するトラブルは比較的よく発生します。これらのトラブルを解決するための一般的な手順を以下にまとめました。
1. 契約内容の確認
- 手順: 賃貸契約書と原状回復に関する特約を確認します。契約書には、敷金返還や原状回復に関する具体的な条件が記載されていることが多いため、まずはその内容を把握しましょう。
2. 現状確認と記録
- 手順: 退去時の物件の状態を詳細に記録します。写真やビデオを撮影しておくと、後でのトラブル防止に役立ちます。特に、入居時の状態と比較できる資料がある場合は、それを基に現状を確認します。
3. 敷金返還の請求
- 手順: 退去後、家主または管理会社に対して敷金の返還を求めます。この時、敷金から差し引かれるべき項目や金額について詳細な説明を求め、必要であれば請求書を発行してもらいましょう。
4. 交渉と話し合い
- 手順: 敷金の返還額や原状回復費用に納得できない場合は、家主や管理会社と直接交渉を行います。この際、根拠を明確にして相手に説明することが重要です。交渉の際には、感情的にならず、冷静に話し合うよう心掛けましょう。
5. 第三者の介入
- 手順: 交渉が難航した場合、第三者の介入を求めることができます。例えば、自治体の消費生活センターや、弁護士、不動産トラブルに詳しい専門家に相談することが考えられます。また、調停や仲裁を利用することで、解決に向けたアドバイスや調停を受けることもできます。
6. 法的手段の検討
- 手順: 話し合いや調停でも解決が難しい場合、法的手段を検討します。敷金返還や原状回復の問題については、簡易裁判所での訴訟を起こすことができます。この際、弁護士に相談して、訴訟の可能性や費用、手続きについて確認しましょう。
7. 問題解決後のフォローアップ
- 手順: 問題が解決した後は、その結果を文書で記録しておきましょう。返還された敷金や支払った原状回復費用の領収書を保管し、将来の参考にします。また、同様のトラブルを避けるために、次回の賃貸契約時には契約内容をより慎重に確認するようにしましょう。
消費生活センターの上手な利用法
ご利用者の中には、消費者センターの相談員に対して「役に立たない」という不満の声があることも事実です。特に、期待する回答が得られなかったり、問題解決が思うように進まなかったりすると、不満が生じやすくなります。しかし、消費者センターは中立的な立場でアドバイスを提供しており、全てのケースで希望通りの結果を得られるわけではありません。そのため、現実的な期待を持ち、冷静に対応することが大切です。
消費者センターを利用する際には、冷静かつ効果的に対応することが重要です。以下に、消費者センターの上手な利用の仕方についてのポイントをまとめました。
1. 冷静に対応する
- ポイント: 消費者センターに相談する際には、感情的にならずに冷静に対応することが大切です。感情的な訴えは問題解決を難しくすることがあり、相談員とのコミュニケーションがスムーズに進まなくなる可能性があります。
2. 説明資料を整える
- ポイント: 相談する内容に関連する契約書、請求書、メールのやり取りなどの証拠資料を整えておくことが重要です。これらの資料をもとに、具体的な事実を整理し、論理的に説明できるように準備しましょう。これにより、相談員が状況を正確に把握しやすくなります。
3. 相談内容を整理する
- ポイント: 問題の経緯や具体的な相談内容を事前に整理し、要点を簡潔に伝えられるようにしておきましょう。無駄な情報や枝葉末節にこだわらず、核心となるポイントを明確に伝えることが、効果的な相談の第一歩です。
4. 中立的な回答を期待する
- ポイント: 消費者センターは中立的な立場で問題解決をサポートします。相談者にとって不利な情報や、期待する結果が得られない場合もあります。そのため、消費者センターが常に自分の立場を支持してくれるわけではないことを理解し、現実的な期待を持つことが重要です。
5. 法的知識や手続きを把握する
- ポイント: 消費者センターは、問題解決に向けた法的な助言や手続きを教えてくれることがあります。基本的な消費者保護の法律や手続きについて、予め理解しておくと、相談がよりスムーズに進みます。
6. 問題解決の選択肢を理解する
- ポイント: 消費者センターは、法的手段だけでなく、和解や調停など、さまざまな解決方法を提案してくれることがあります。自分の求める結果に最適な解決方法が何かを相談員と一緒に考えることが、問題解決への近道です。
7. 相談員の指示に従う
- ポイント: 相談員が提案する解決策や次のステップに従って行動することが大切です。相談員は豊富な経験と知識を持っており、彼らの指示に従うことで、問題解決の可能性が高まります。
8. 相談後のフォローアップ
- ポイント: 相談後も、自分自身で問題の進捗を追跡し、必要に応じて再度相談することが求められます。解決が長引く場合もありますので、粘り強く対応し、進展がない場合は適切なタイミングで再度相談することが重要です。
=ご提案1=事前に知識を身に付けておくことスムーズ
賃貸トラブルを未然に防ぎ、円滑に対応するためには、事前に必要な知識を身につけておくことが重要です。特に、原状回復費用や敷金返還に関するトラブルを防ぐためには、信頼できるガイドラインや専門機関の情報を参考にすることが役立ちます。国土交通省や各自治体が提供しているガイドラインや、消費生活センターの相談窓口を活用する方法について以下で解説します。
これらのポイントに注意することで、消費者センターをより効果的に活用し、トラブルを解決するためのサポートを最大限に受けることができます。
参考になるガイドライン
1. 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
国土交通省が策定したこのガイドラインは、賃貸住宅退去時の「原状回復」の範囲について詳しく説明しています。
- ポイント:
- 借主が負担するのは「通常の使用による劣化・損耗を除いた、過失や故意による損傷のみ」。
- 具体的な例(壁紙の色あせ、床の擦り傷など)が記載されており、トラブル解決の判断基準になります。
- 閲覧方法: 国土交通省の公式ウェブサイトでPDFが無料公開されています。
ガイドライン閲覧ページ(PDF)
2. 東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」
東京都では、都内の賃貸物件におけるトラブル防止のための独自ガイドラインを作成しています。
- ポイント:
- 原状回復に関する説明に加え、契約時の注意点や更新料についても触れています。
- 東京都内の事例に基づいて作られているため、地域特有のトラブル解決に役立ちます。
- 閲覧方法: 東京都の公式ウェブサイトで公開されており、PDF形式でダウンロード可能です。
東京都住宅政策本部(PDF)
=ご提案2=別の無料相談先で相談してみる
1. 不動産関連の専門団体
不動産業界に関連する専門団体は、賃貸トラブルの相談窓口を設けている場合があります。これらの団体は、不動産契約やトラブルに関する具体的な知識を持っており、専門的なアドバイスを提供してくれます。
- 全国賃貸住宅経営者協会連合会(全宅連)
- 賃貸経営に関する知識を広める団体で、借主・貸主双方のトラブル相談に対応。
- 地域ごとに支部があり、トラブルに即したアドバイスを提供。
- 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
- 賃貸物件の原状回復やリフォームに特化した相談機関。
- 「住まいるダイヤル」(0570-016-100) では、原状回復に関する法律や適正な費用の範囲について具体的な相談が可能。
- 各団体の公式ウェブサイトや相談窓口にアクセスし、必要書類を準備して相談を申し込む。
- 一部の団体では、メール相談や電話相談を受け付けています。
2. 法テラス(日本司法支援センター)
法テラスは、法律に関する相談や支援を行う公的機関です。敷金や原状回復費用のトラブルが法的な問題に発展した場合、解決のための具体的な手段を提案してくれます。
- 無料法律相談
- 一定の条件を満たせば、無料で弁護士や司法書士による相談を受けられます。
- 原状回復や敷金返還の不当請求について法的観点から判断を提供。
- 裁判手続きの支援
- 交渉や話し合いが決裂した場合、裁判手続きに関する支援を受けられます。
- 費用負担が難しい場合には、弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用可能。
- 法テラスの相談窓口に電話(0570-078374)で予約。
- 公式ウェブサイトでオンライン相談を申し込むことも可能。
- 必要書類(契約書やトラブルの記録)を持参し、面談相談を受ける。
まとめ
- 不動産関連の専門団体は、賃貸トラブルの初期段階での相談や、業界の慣行を踏まえた具体的なアドバイスを提供。
- 法テラスは、トラブルが法的問題に発展した場合に、専門的な法的支援や裁判手続きのサポートを提供。
ゴミ屋敷で原状回復トラブルを自分で解決するための7つの流れ
1. 国土交通省の「原状回復ガイドライン」を学ぶ
まず初めに確認すべきは、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。この資料には、借主が負担すべき修繕の範囲や考え方が明確に記されています。
通常の使用で発生する傷や汚れ(通常損耗)は貸主負担であり、借主が全てを修繕する必要はないことがわかります。トラブル予防・交渉時の土台となる知識として必ず把握しておきましょう。
2. ゴミ撤去後の「写真記録」を残す
ゴミ屋敷の状態から片付けを行った場合、その清掃後の部屋の状態を証拠として記録することが重要です。
作業前・途中・完了後の3段階で撮影し、傷・汚れの場所や程度を明確に記録しておくことで、後々「汚れが残っていた」と不当な請求をされても反論できます。
3. 退去時には必ず「立ち合い」をする
退去当日は、必ず自分が立ち会うことが大切です。業者や管理会社に任せきりにすると、現場でのやり取りが不透明になりがちです。
実際に担当者と一緒に室内を確認し、どの部分が修繕対象とされるかをその場で確認し、メモや写真を残しておきましょう。納得できない点はその場でしっかり質問を。
4. 原状回復費用の「見積書と明細」をもらう
修繕費の請求を受けた場合は、必ず明細付きの見積書を依頼してください。
「原状回復費用:一式 25万円」などといった曖昧な表記ではなく、内訳(クロス張替え・床の修繕・清掃など)とそれぞれの単価を明示してもらいましょう。あやふやな部分は、具体的な根拠を求めることが重要です。
5. ガイドラインに沿って見積もりを精査する(経過年数も確認)
提出された見積もりが、ガイドラインの基準に従っているかどうかを冷静に確認します。
特に注目すべきは、「経過年数(耐用年数)の考慮」がされているか。たとえばクロス(壁紙)は6年で価値がゼロになるとされており、それ以降の張替え費用を借主が全額負担するのは不当です。
過剰な請求になっていないかを判断するため、ガイドライン+経年劣化の基準を照らし合わせて判断しましょう。
6. 修繕費について冷静に「交渉」する
見積もりに納得がいかない場合は、ガイドラインや写真記録を根拠に交渉を行います。
「この修繕は経年劣化に該当するのでは?」「この金額は相場よりも高すぎるのでは?」といった形で、感情的にならず論理的に伝えることが大切です。
やり取りはなるべくメールなど記録が残る形で行いましょう。
7. 話し合いができない場合は「少額訴訟」を検討
交渉がうまくいかず、理不尽な請求が続くようであれば、簡易裁判所での少額訴訟や調停を視野に入れましょう。
少額訴訟は60万円以下の請求で使える制度で、1回の審理で判決が出るため、時間や費用をかけずに解決が期待できます。
準備としては、
- 写真記録
- 見積書・契約書
- ガイドラインの抜粋
- やり取りの記録(メールやLINEなど)
をまとめておくと安心です。
✅まとめ:証拠と知識で冷静に対応すれば、防げるトラブルです
原状回復トラブルは、「知らないこと」が一番の損失につながります。
事前にガイドラインを理解し、証拠を揃えて、感情的にならず粘り強く対応すれば、不当な請求に対してしっかり自分を守ることができます。
さらに、詳しいコラムは、現状回復トラブル。弁護士に頼らない、自分で交渉・解決するできる をあわせてお読みください。(自社外部サイト)
《PR》アパート退去なら、引越しと廃棄を一緒にできる業者をお探しなら

鶴ヶ島市、川越市、坂戸市方面でアパートからの退去・引っ越しをお考えでしたら、立ち合い無しでも安心してご利用いただけます。荷物の廃棄や配達、退去の事務手続きも全て無料で行います。お支払いは後払いなので、不安なくサービスをご利用いただけます。私たちはお客様のニーズに合わせたスムーズなサービス提供に努め、安心して新生活のスタートをサポートいたします。お気軽にご相談ください。➡店舗案内
当社へのご相談・お問合せ
「今の状態でも対応できるか」「どれくらいで空っぽになるか」
その確認だけでも構いません。
電話一本で状況を伺い、できること・難しいことを整理してご案内します。
無理な営業や催促は行っていませんので、まずはお気軽にご相談ください。
当社のお部屋片付け代行地域のご案内
営業エリア内では、見積もりはすべて無料で対応しています。
また、退去期限が迫っている場合や急な引越しなど、お急ぎのご相談にも状況に応じて柔軟に対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
埼玉県のサポート地域
全地域で即日でお見積り、作業も対応しています
上尾市・朝霞市・越生町・三芳町・毛呂山町・入間市・寄居町・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・杉戸町・松伏町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・上里町・美里町・岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑・南区・見沼区・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・白岡市・草加市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・羽生市・飯能市・東松山市・小川町・川島町・滑川町・ときがわ町・鳩山町・吉見町・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・本庄市・三郷市・宮代町・八潮市・吉川市・和光市・蕨市・秩父市・伊奈町・嵐山町
東京都のサポート地域
離島を除き全地地域スピード対応しています。
昭島市・あきる野市・足立区・荒川区・板橋区・稲城市・江戸川区・青梅市・大田区・葛飾区・北区・清瀬市・国立市・江東区・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・品川区・杉並区・墨田区・世田谷区・立川市・台東区・多摩市・調布市・豊島区・中野区・奥多摩町・日の出町・瑞穂町・西東京市・練馬区・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・武蔵村山市・日野市・府中市・福生市・文京区・町田市・三鷹市・港区・武蔵野市・目黒区
神奈川県のサポート地域
横浜・川崎・東京よりで対応しています。
厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・鎌倉市・川崎市・川崎市麻生区・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市中原区・川崎市宮前区・相模原市(緑区、中央区、南区)・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・藤沢市・大和市・横須賀市・横浜市青葉区・横浜市旭区・横浜市泉区・横浜市磯子区・横浜市金沢区・横浜市南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市港南区・横浜市都筑区・横浜市鶴見区・戸塚区・横浜市中区・横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市緑区・横浜市南区・神奈川区
千葉県のサポート地域
東京・埼玉よりで千葉県の7割をカバーしています
我孫子市・市川市・市原市・印西市・浦安市・柏市・鎌ヶ谷市・白井市・流山市・習志野市・野田市・船橋市・松戸市・八千代市・四街道市・佐倉市・千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)
群馬県・茨城県・山梨県のサポート地域
東京・埼玉・千葉寄りで専任者がスピード対応しています
【茨城県】常総市・坂東市・守谷市・取手市・つくばみらい市
【群馬県】高崎市・安中市・富岡市・藤岡市・伊勢崎市・前橋市・みどり市・太田市・桐生市・吉岡町・渋川市・館林市・邑楽町
【山梨県】上野原市・大月市・都留市・山梨市・甲州市・笛吹市・甲府市